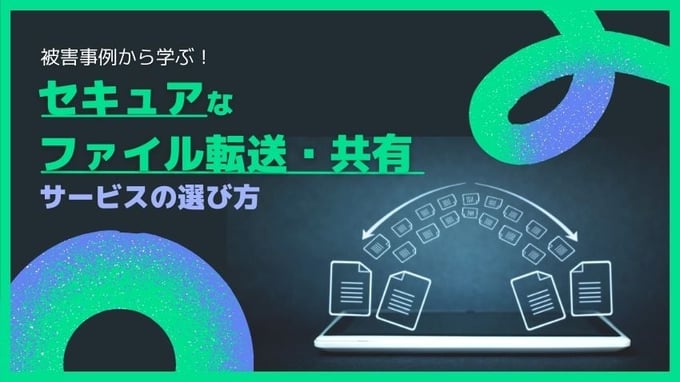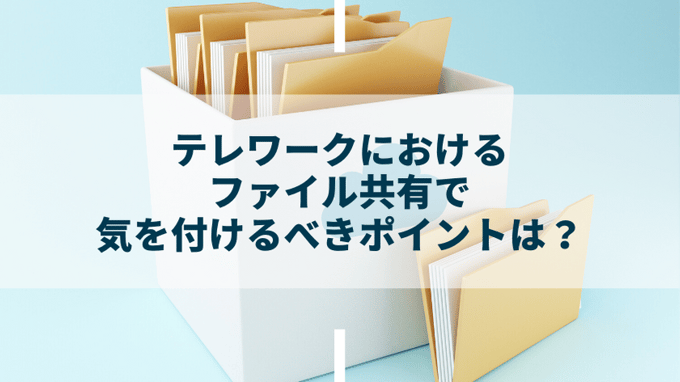導入の背景や課題
機密書類の受け取りを安心して行えるセキュアなサービスとは
 埼玉県信用保証協会 保証経営支援部 保証統括課 主事 千葉 廉氏
埼玉県信用保証協会 保証経営支援部 保証統括課 主事 千葉 廉氏
当協会へ申込等を行う事業者は、金融機関を経由して申込書や確定申告書などの決算書類を提出します。金融機関は、事業者から紙媒体にて受領した決算書等を当協会へ郵送もしくは持ち込みいただき、当協会側では、郵便で受け取った決算書をスキャンし、管理システムに入力した後、提出書類を廃棄する作業を行います。1件あたりの対応は5~10分程度ですが、年間に提供される決算書は約4万件以上になるため、コストおよび事務負担軽減を目的としたファイルの電子共有を検討していました。
私たちが取り扱う決算書等の書類は、重要な経営情報が掲載されている機密書類に該当しますので、デジタルでのファイル共有に際しては、堅牢なセキュリティ環境であることが不可欠です。また、金融機関に協力していただく必要があるため、どのようなサービスを利用すべきか検討していたところ、取引先である金融機関の担当者との会話を通じて、クリプト便の認知度が高いことが分かりました。端末認証が可能である点や、送付先の都度指定が不要で誤送信の抑止ができる点、データセンターが日本国内にある点なども決め手となり、クリプト便のファイル共有サービスを採用することになりました。
選定のポイント
金融機関ごとの運用に合わせて、アカウント発行数を選択できる柔軟性
 埼玉県信用保証協会 保証経営支援部 保証統括課 課長 内野 卓氏
埼玉県信用保証協会 保証経営支援部 保証統括課 課長 内野 卓氏
当初は各金融機関でクリプト便を契約・導入いただくことも検討していましたが、各金融機関と意見交換をする中で、今後も利用を拡大していくたびにクリプト便の契約が必要になるのは現実的ではないと考えました。そこで、当協会がNRIセキュアテクノロジーズ(以下、NRIセキュア)と契約して必要なアカウント数を購入し、提携先の金融機関にはアカウントごとの費用負担をいただく形で導入することになりました。(図参照)
当協会で契約しながら、利用方法は金融機関ごとの事情に合わせて柔軟に設定できる点も大きなポイントでした。ネットワーク環境やワークフローは金融機関によって異なります。金融機関によっては、支店から外部ネットワークへのアクセスができないケースもあります。また、決算書の登録作業についても、受け付けた支店ごとに行う金融機関と、本店で集約している金融機関がありました。そのためアカウントを発行するにあたり、本店用のアカウントのみで良い金融機関と、支店分のアカウントが必要になる金融機関がありましたが、クリプト便は、アカウントに対する端末認証の適用など必要なセキュリティポリシーを維持しながら、そのいずれにも対応することができました。

導入の効果
全体の6~7割がデジタル化の見込み。提供数増加により経営支援業務もスムーズに

導入後もトラブルなく安定的に稼働しています。県内に本店を置く8つの金融機関とクリプト便の運用を予定していますが、現時点では5つの金融機関で利用開始しています。予定している全ての金融機関で導入ができるようになると、全体のおよそ6~7割に相当する決算書をデジタルで受け取れるようになる見込みです。
また、クリプト便の導入によって金融機関側での決算書提出にかかる負担が下がったことで、決算書の提供数が、導入前と比較して約2割増加しています。我々は保証後に経営支援も実施しており、決算書が増えることやタイムリーに受け取れることは嬉しいことしかありません。新規保証の申し込み時の提供に加えて、継続的な経営支援を行うための業務運営も非常にスムーズになりました。
今後の展望
全国の保証協会からもデジタル化の取り組みが注目される存在に
私自身は、セキュリティやITに関する知識がほとんどない状態で、担当者として各種対応をすることになりましたが、NRIセキュアの皆さんは不明点や初歩的な質問にも分かりやすく支援してくださいました。現在、クリプト便は決算書等に限定した利用となっていますが、今後はその他の書類についても利用して行く予定です。また、県外の金融機関や商工団体に対しても利用を拡大し、さらなる事務コスト・事務負担の軽減を図っていきたいと考えています。
全国に保証協会は51ありますが、私たちがこの取り組みを始めた際には、これらのデータ受け取りに際して、デジタル化を行っている保証協会はほとんどありませんでした。取り扱うのが機密情報であることや、複数の金融機関との連携・協力はもちろん、各金融機関の環境に合わせた対応なども必要になるため、デジタル化に対してはハードルが高く、どうしても慎重になる面があると思います。当協会は経営陣からも「DXを進めてほしい」とリクエストをもらっていたこともあり、今回デジタル化にチャレンジしましたが、全国に先んじて取り組んだことで、現在は他県の保証協会からも頻繁に照会をいただくようになっています。これを機に全国の保証協会ともDXに向けた取り組みをシェアしていけたら幸いです。
※本文中の組織名、職名は2025年7月時点のものです