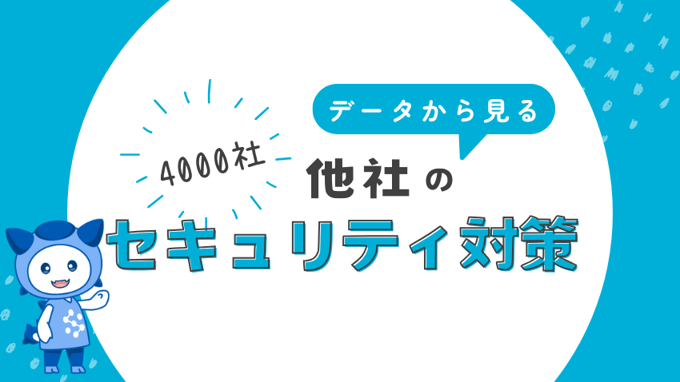導入の背景
見えない点が多かったグループ全体のセキュリティ。経営に対して全体俯瞰での回答ができず苦心していた
グループIT ガバナンス部 サイバーセキュリティ戦略室 室長 押原 弘明氏
日清食品ホールディングスでは、グループ全体のITガバナンスを統括する専門部署として「グループITガバナンス部」を設置しています。同部では、外部からの脅威対策やセキュリティ統制を担う「サイバーセキュリティ戦略室」と、グループ各社との連携や現場対応を担う「ITガバナンス室」が両輪となり、国内外のグループ会社全体のセキュリティ施策を推進しています。(2025年6月18日取材時)
今回は、このセキュリティ施策を推進するサイバーセキュリティ戦略室室長・押原弘明氏と、同室の池谷俊輔氏にお話を伺いました。
同社がSecure SketCHの導入検討を開始したのは2023年。当時抱えていた課題を押原氏が語ります。
昨今、国内外を問わずサイバーセキュリティ被害が深刻化しており、当社としても対策は急務でした。各グループ会社のセキュリティ対策について様々な手段を模索していましたが、全体最適を見据え、優先度付けや計画策定から考える必要があったのです。経営層からの「私たちのグループ全体のセキュリティは大丈夫なのか?」という問いに、全体俯瞰でより定量的に把握できる状態にすることが大きな課題でした。
特に課題となっていたのが、インシデント発生時の対応体制でした。
有事の際に、各社で具体的に誰が動くのか、そもそも対応の手引きは存在するのか、といった点が非常にブラックボックス化していました。予防的な対策はもちろん重要ですが、万が一の事態に迅速かつ的確に対応できる体制が整っているかどうかが把握できていない。これは統制面における大きな課題でした。
こうした状況を打破し、グループ全体のセキュリティ状況を可視化した上で対策の優先度付けを行うため、同社はSecure SketCHの導入を決定しました。
選定のポイント
複数ガイドラインへの対応と見やすいダッシュボード。そして“共通言語”となり得るベストプラクティスが決め手に
数あるツールの中からSecure SketCHの採用に至った決め手は何だったのでしょうか。
まず大きな決め手となったのが、主要な複数のガイドラインを幅広くカバーしていた点です。NIST CSFやISO 27001といったグローバルスタンダードはもちろん、我々が当時ベースとしていた経済産業省のサイバーセキュリティ経営ガイドラインも網羅されていました。こうしたガイドラインは常に内容が改訂されていきますが、その最新動向を継続的に追い続けるのは専門家でなければ容易ではありません。Secure SketCHは、そうした頻繁な改訂にも追随し、最新の内容を適時反映してくれるため、非常に魅力的でした。
加えて、評価結果を可視化するダッシュボードの見やすさもポイントでした。最初に見たとき、単純に「見やすいな」と感じたのを覚えています。時系列でスコアや偏差値の変化がグラフで表示されるので、直感的に理解できます。
そしてもう一つ欠かせなかったのが、各評価項目に専門家の知見に基づいた「ベストプラクティス」が提案されていることです。
このベストプラクティスの存在が、後にグループ全体のコミュニケーションを円滑にする上で大きな役割を果たすことになりました。

グループIT ガバナンス部 サイバーセキュリティ戦略室 プロフェッショナル 池谷 俊輔氏
導入の効果1
国内外のグループ会社、そして監査部門とも連携。“共通言語”が組織の壁を超える
Secure SketCHの導入は、同社のセキュリティ対策に大きな変化をもたらしました。
まず、これまで見えていなかったグループ全体の課題が明確になりました。
Secure SketCHによるアセスメントで、グループ全体の共通課題が浮き彫りになりました。特に『ポリシーや規定の整備』『全社的な教育』『インシデント対応体制の構築』が急務であると判明し、これらを本社主導の重要施策として推進しました。この動きが、全社的なインシデント対応体制であるNISSIN-CSIRTの立ち上げに繋がっています。
同社の取り組みで特徴的なのは、こうしたセキュリティ施策を従業員に周知する際の、クリエイティブで親しみやすいアプローチです。

図1.社内のデザイン部門と連携して制作したCSIRTのロゴとロゴに込められたメッセージ
ロゴを社内掲載し「何かあったらCSIRTへ」の意識づけを実施
コミュニケーションの面でも大きな効果が現れています。Secure SketCHは、専門知識のレベルが異なる部門間や、言語の壁がある海外拠点とのやり取りにおいて、まさに“共通言語”として機能しています。
月一の定例会や年一のアセスメントの場で、Secure SketCHを中心に据えて、具体的なセキュリティ議論がなされるようになりました。例えば、技術担当とガバナンス担当では専門知識に差がありますが、Secure SketCHの画面を見ながら「今話しているのはここの項目ですね」と目線を合わせることで、議論がスムーズに進みます。
特に海外拠点とのコミュニケーションでは、この効果は大きいです。
さらに、日清食品グループでのSecure SketCHの活用法で特筆すべきは、監査部門との連携です。
これは、リスク管理と統制のための代表的なフレームワークである「スリーラインモデル(三線モデル)」(※)を、Secure SketCHというプラットフォーム上で実現した先進的かつ合理的な事例と言えるでしょう。
※スリーラインモデル:ビジネス部門(一線)、統制・管理部門(二線)、内部監査部門(三線)がそれぞれ役割を担い、連携してリスク管理を行う考え方。

図2.現場・統制部門・監査部門のスリーラインと経営が連携し、組織全体でリスクに対応する体制を構築・推進
導入の効果2
柔軟なカスタマイズで独自の課題に対応。セキュリティ管理をワンストップで実現
Secure SketCHは、セキュリティ統制をリードする統括部門が、企業独自の設問項目をオリジナル設問として各社へ回答依頼ができるテンプレート評価も備えています。日清食品グループではこの機能を活用し、独自のセキュリティ管理プラットフォームとして昇華させています。
テンプレート評価機能の便利な点は、状況に応じて柔軟に使えるところです。例えば、有事の際に独自の設問でグループ全体の状況を一斉に調査したり、あるいは内部不正対策のように特定のテーマを想定して独自の設問を追加したりと、様々な使い方ができます。これまではExcelや別のフォームを使って情報を収集していましたが、最終的に情報を一元化する場所としてSecure SketCHがあるのは非常に大きいです。「セキュリティに関する回答は、Secure SketCHでお願いします」と言えば済みますし、証跡も合わせてアップロードしてもらえるので、管理がとても楽になりました。
このような活用の広がりを支えているのが、Secure SketCHの料金体系です。
今後の展望
信頼=競争力。これからのセキュリティ戦略も、日清らしく、クリエイティブに
Secure SketCHの活用により、グループ全体のセキュリティガバナンスを新たなステージへと引き上げた日清食品グループ。今後の展望について、両氏は次のように語ります。
事業会社において、人が入れ替わっても高いレベルのセキュリティを「継続」していくことは、自社だけの力では非常に困難です。NRIセキュアには、我々の弱点を補ってくれる専門的な知見と、経営判断の際に客観的な視点で伴走してくれるパートナーとしての役割を引き続き期待しています。他社の事例なども参考にしながら、常により良い対策を検討していきたいです。
こうしたセキュリティへの真摯な取り組みを積極的に外部へ情報発信していくことが、日清食品グループにとっての重要な活動の一つだと両氏は考えています。
日清食品グループには、創業者・安藤百福氏の精神を受け継ぐ、ユニークで創造的な企業DNAが息づいています。その姿勢は、一般的に守りのイメージが強いサイバーセキュリティの領域においても貫かれており、ITリテラシーのレベルが様々な従業員に向けた啓発活動から有事のインシデント対応まで、随所に同社ならではのスピリットが反映されています。
最後に、セキュリティにおける「日清らしさ」について、両氏に語っていただきました。

前列左から池谷氏、押原氏(日清食品ホールディングス様)
後列左から瀬戸、濱田、長谷川、足立(弊社)
※本文中の組織名、職名、概要図は2025年6月時点のものです。