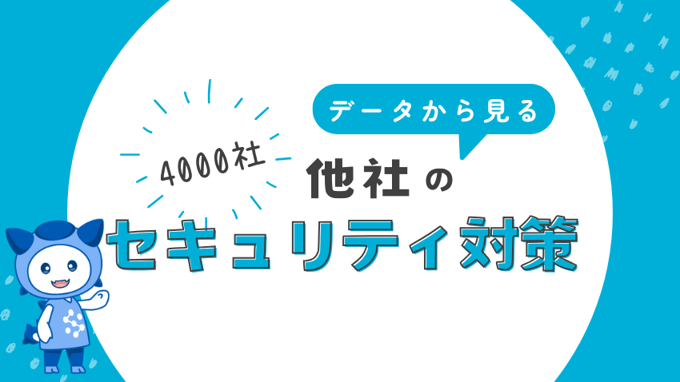導入の背景
グループ横断での客観的・継続的な評価を求めてNIST CSFを採用
 グループデジタルソリューションセンター
グループデジタルソリューションセンター
ネットワーク・ITセキュリティチーム 課長 飯原 亮央氏
ポーラ・オルビスホールディングスは、グループ横断の情報セキュリティ委員会を発足し、専任チームを設立したことで、グループ内でのセキュリティ強化施策を実施できる体制を整備しました。一方で、効果的な施策を推進するための基盤となるグループ各社の現状把握に課題がありました。
グループデジタルソリューションセンターネットワーク・ITセキュリティチーム課長の飯原亮央氏は、当時の状況について次のように振り返ります。
体制は整ったものの、当時はグループ各社のセキュリティ対策状況が見えていませんでした。そのためグループ内の対策状況を数値化し、網羅的に強化施策を実施できる仕組みの必要性を感じていました。
以前より、他のベンダーが提供するスポット支援型の評価サービスを受けたことはありましたが、そのベンダーが考える独自の基準を用いた評価であったため、必要な対策の根拠や継続性に疑問を感じることがありました。
我々が求めていたのは、グローバルで一般的に使われているスタンダードなフレームワークを用いて、定量的かつ客観的な評価を継続的に実施することでした。そこで選定したフレームワークが、NIST CSFです。
NIST CSFの採用プロセスについては、同社の組織文化が大きく影響しています。
部内でNIST CSFの採用を立案し、取締役会での承認を得て最終決定しました。経営陣としてもNIST CSFの採用については前向きでした。当社には現場からの提案を経営陣が積極的に支援してくれる組織文化があり、今回も現場発の取り組みとして推進することができました。
選定のポイント
なぜSecure SketCHだったのか。NIST CSF準拠と他社比較の両立が決め手に
2023年7月にツール選定を開始した際、同社が重視したのは運用面での実用性と、客観的かつ継続的な評価の実現でした。 飯原氏は選定の決め手について詳しく説明します。
Web上で評価でき、大きな費用はかからず、自分たちで運用ができること、これらの要件にSecure SketCHが合致していました。さらに、ベンダー独自ではなく一般的に利用されるセキュリティ基準を用いること、なおかつ評価結果の他社比較ができる点が魅力的でした。
経営層への報告においても「当社はどれくらいできているのか、どれくらいを目指すべきなのか」というNIST CSFの評価値(Tier1~4)での見える化が必要でしたが、それ以上に重要だったのは、そのTier値の根拠と妥当性を示すことでした。
そこでNRIセキュアは、統計データを用いて他社と比較ができるSecure SketCHの強みを活かし、Secure SketCHの1000満点中のスコアとNIST CSFの評価値(Tier1~4)を同時に算出できる評価支援を提案しました。
図. Secure SketCHの評価とNIST CSF 2.0の評価を一度に実現する評価支援を提案

このNRIセキュアの提案がなぜ決め手となったのか。ネットワーク・ITセキュリティチームの山本佑美氏が補足します。
NIST CSFのTier値で表現した評価は本来、私たちが実現したいことでした。しかしながら、世の中にTier値に関する統計データがないため、他社と比較することができず、評価結果が妥当か分からない・ベンチマークできないという悩みがありました。
一方、Secure SketCHの強みは統計データとベンチマーク機能です。
つまり、NIST CSFに準拠しているためTier値を用いた評価ができ、同時にSecure SketCHが持つ1000点満点評価でベンチマークもできる、この両方を同時に実現する仕組みにより、NIST CSFに準拠しながら業界内での立ち位置も把握できるという、まさに理想的なソリューションを提供していただけました。グループデジタルソリューションセンター
ネットワーク・ITセキュリティチーム 山本 佑美氏
NIST CSF 2.0専用設問をグループ22社に展開。伴走支援と運用の工夫
導入決定後、NRIセキュアからは技術面だけでなく、運用面での柔軟な支援体制も提案されました。
2023年から、当社の各年の業務計画に合わせた柔軟かつスピーディな支援スケジュールを提案していただいています。特に2024年にNIST CSFのバージョンが 2.0への改定が行われた際も、NRIセキュア側にノウハウと技術的な蓄積があったため、新しいバージョンに対応した設問へ即座に更新いただけました。
NRIセキュアから提案された最大400問の設問について、当初は量の多さに戸惑いもありました。しかし設問を何度も読み込むことにより、どういったセキュリティ対策が求められるのか、その理解が深まったことで、結果的にグループ会社に対して行う回答支援においても役立ちました。
また、NRIセキュア側からは運用面での工夫についてもご提案いただきました。たとえば、ある設問を表示するかどうかを、前の設問の回答内容に応じて制御する「設問の表示条件」を設定したり、ポリシーやインフラに関する設問などは、事前に親会社の回答を子会社に適用したりすることで、子会社が実際に回答する設問数を100~200問程度にまで削減することができました。こうした工夫により、各社の回答負担を大幅に軽減することができました。
導入の効果1
NIST CSF 2.0に対応した包括的な評価でグループ課題の全貌が明らかに
グループ22社への包括的な評価プロジェクトにより、これまで見えなかった組織全体の状況が明らかになりました。
飯原氏は評価結果から得られた具体的な気づきについて語ります。
グループ全体の強み・弱みが可視化され、どの領域で目標値との差が大きいかが明確になりました。特に良かったのが、セキュリティ製品の標準化や一元管理など、各社でバラバラに運用していては改善効率が悪い領域を特定できたことです。
また評価結果をもとに優先すべき対策を明確化して、それらの対策を実施した場合の予測結果を算出できるので、具体的な改善計画の策定に役立っています。
図. グループ全体の評価結果を算出(Sample、数値はイメージ)

この成果は、グループ各社の意識と行動に変化をもたらしたようです。
各社の弱みが可視化されたことで、各社から「改善するためには具体的にどういった対策が必要か」といった相談が積極的に寄せられるようになりました 。特に「せっかく回答したこの評価データを、今後のアクションプラン策定に活用したい」という声が多く挙がっています。
例えば、自社の評価結果を基に、どの項目を改善すればスコアがどれだけ向上するのかというシミュレーションをふまえて次年度の計画を立てたい、といった具体的な相談です。また、評価スコアが高い企業の取り組みを参考にしたいという意見も出ており、グループ全体で好事例を共有し、共にレベルアップしていこうという機運の高まりを感じています 。
導入の効果2
NIST CSF 2.0 Tier値とSecure SketCHスコアの併用で経営層への説明力が飛躍的に向上
今回の取り組みで最も画期的だったのは、NIST CSF 2.0のTier値とSecure SketCHのスコアを同時に出力する仕組みの構築です。この併用アプローチが、特に経営層への報告において大きな効果を発揮しています。
SketCHのスコアを利用し業界と比較したことで、現状のTier値、及び目標値がどの程度の水準なのかを、誰でも分かる形で経営層に対して報告することができました。
NIST CSF 2.0のTier値だけでは「これが良いのか悪いのか」という基準が分からないのですが、Secure SketCHの統計データと組み合わせることで「業界平均と比較してこの位置にいる」「目標値は業界内でこのレベルに相当する」といった説得力のある説明が可能になりました。
実際に経営陣からも「この指標なら理解しやすい」と高く評価されており、ある役員からは「Secure SketCHが算出するこの評価は、報告書の冒頭に持ってくるべきだ」とのコメントももらうほどで、経営層がこの取り組みの重要性を深く理解してくれている証だと思います 。
導入の効果3
工夫された運用と機能の有効活用で、海外拠点への展開もセルフで対応が可能に
また運用面でも、システムの特性を活かした効率的な管理が実現しています。
各社の評価値や目標値が可視化できたことで、グループ各社、経営層含め、共通の認識が持てるようになりました。ベンダーに頼らないセルフアセスメントですので、当社都合で評価の実施時期が調整できるため、例えば予算策定時期に合わせるなど柔軟に運用できています。
各社の回答状況がSecure SketCH上ですぐ確認できるため、進捗管理やコメント機能を使った各社とのやりとりもスムーズ。また、言語切り替えが可能なため、海外個社への展開のハードルも大幅に下がりました。
図. 各社の設問に対する回答進捗状況を、Secure SketCH上で確認・管理などできる
海外拠点での運用については、特有の困難もありましたが、工夫することで対応しています。
日本と比べIT組織の規模が異なり、IT専任担当者がいない会社もあります。海外各社のインフラやアプリケーションなどの情報がほぼない状況からスタートしましたので、担当者の工数確保、各社の販売チャネル・インフラ・アプリなど一からヒアリングが必要でした。
日本の数倍の回答支援・レビューが必要で、全問チェックし、認識違いを全て説明するなど大変でしたが、最終的には中国語、英語、タイ語、日本語の4言語で運用することで、海外拠点を含めた統一的な評価を実現できました。
今後の展望
「共通課題→個別課題」へ段階的アプローチによりセキュリティ対策強化を効率的に実現
今後のセキュリティ成熟度向上に向けて、同社はどのような戦略を描いているのでしょうか。飯原氏は段階的なアプローチについて次のように説明します。
特に、NIST CSF 2.0で新たに追加された「Govern(統治)」の考え方は重視しています。この機能で定義されているリスクの特定・分析・評価をグループ全体で着実に実施し、社会情勢の変化も迅速に反映しながらポリシーを継続的に見直す体制を整備していく予定です。
この部分は、まさに我々が目指すグループ共通のガバナンス強化そのものであり、NIST CSF 2.0の強化ポイントを活用して、より堅牢な体制を築いていきます。
Secure SketCHへの期待と、同様の課題を抱える企業へのメッセージ
飯原氏には、Secure SketCHの現在の運用における課題と、今後の期待も語っていただきました。
現状では、NIST CSF 2.0のTier値を算出するためには、個別にNRIセキュア側に依頼が必要です。将来的には、ぜひSecure SketCH上で自動的に算出できるように機能を開発いただきたいです。
設問に回答した各社からも「とにかく結果を早く見たい」という希望が多く寄せられています。それだけでなく、例えば回答ミスを修正した結果をすぐに確認したり、ある改善策で評価値がどう変わるか予測したりする場合にも、入力後すぐに結果が表示される機能があると、本当に助かります。
各社がリアルタイムで点数の変化を確認できれば、グループ全体の活動がより活発になるのではないかと期待しています。
山本氏からは、同じような課題を抱える企業に向けて、経験に基づくアドバイスをいただきました。
組織でセキュリティ対策の客観的な評価が求められる場合、Secure SketCHを使ってNIST CSF 2.0への対応状況を数値化するのは、現実的で効果的な方法だと思います。
専門知識がない人にも分かりやすい指標として提示でき、NIST CSF 2.0に沿った改善と再評価のサイクルも構築できます。特に、グローバル展開や複数拠点・子会社を持つ企業では、統一的な評価基準を持つ価値は非常に大きいでしょう。
NIST CSF 2.0という客観的で継続性のあるフレームワークと、Secure SketCHの統計データや使いやすい機能を組み合わせることで、効率的で説得力のあるセキュリティ管理を実現できていると実感しています。
私たちが今回NRIセキュアと構築したこの評価の仕組みは、近い将来、他の企業様にもご利用いただけるサービスとして展開される予定と伺っています。当社と同様の課題をお持ちの企業の方は、試してみる価値があると思います。

前列左から飯原氏、山本氏(ポーラ・オルビスホールディングス様)
後列左から川崎、薮内、宮田(弊社)
※本文中の組織名、職名、概要図は2025年6月時点のものです。