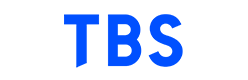導入の背景や課題
各社ばらばらではなく、グループ横断でのデータ利活用による顧客理解の促進へ
 近鉄グループホールディングス株式会社 総合政策部デジタル推進室課長 吉嵜俊介氏
近鉄グループホールディングス株式会社 総合政策部デジタル推進室課長 吉嵜俊介氏
近鉄グループは、暮らしに関わる領域で幅広い事業を展開してきました。今は少子高齢化に伴う人口減少という避けられない課題に対し、デジタルトランスフォーメーション(DX)を活用して価値を高め、対応しようとしているところです。
大きなきっかけは新型コロナウイルスによる生活様式の変化でした。事業ポートフォリオの見直しを余儀なくされ、デジタルデータの利活用をグループ全体で進め、お客様を理解した上で一人一人の嗜好に合わせたアプローチを取り、収益拡大に取り組む必要があると判断しました。
そこで「近鉄グループ中期経営計画 2024」において、お客様とのデジタル接点を統合し、利便性向上とお客様との関係強化、需要創出を図る「デジタルサービスプラットフォーム」の構築を掲げ、推進しています。デジタル活用により、鉄道の路線を拡大するかのように、これまで踏み込めなかった領域への進出が可能になると考えています。
デジタルサービスプラットフォームでは、グループ各社のWebサービスやアプリで利用可能な共通のアカウントとなる「近鉄グループ共通ID(Kintetsu-ID)」、グループ内施設等で利用できるKIPSポイントサービスの新たなデジタル接点となる「KIPSアプリ」、各社で保有する顧客データ、購買データ等を集約し、グループ横断的なデータ利活用を推進する「顧客データ基盤(CDP)」の三つの基盤を軸として取り組みを進めています。特に共通IDの整備については、今後の様々なデジタル接点と顧客データ基盤を繋ぐデジタルサービスプラットフォームの核となるため、先行して取り組む必要がありました。
しかしグループ各社の中にはすでに独自の会員基盤を持つWebサービスも多くあり、顧客データの管理も個社ごとで行っているため、グループ横断的なデータ利活用が難しい状況でした。また、お客様はこうした各社のサービスのアカウントを個別に登録する必要がありました。
既存のアカウントは個々のサービスの認証のためという意味合いが強く、他サービスとの連携やデジタルデータの活用を前提としたものではありませんでした。会員IDとしてメールアドレスを用いるものもあれば、会社側が割り当てたランダムな文字列を使うものもあるという具合に仕様が異なるだけでなく、セキュリティ要件も、個人情報を利用する上で必須の許諾管理もばらばらでした。
選定のポイント
幅広い要件に標準対応できる守備範囲の広さと、将来にわたる提供体制と実績に信頼
 近鉄グループホールディングス株式会社 総合政策部デジタル推進室係長 岡田侑樹氏
近鉄グループホールディングス株式会社 総合政策部デジタル推進室係長 岡田侑樹氏
Kintetsu-IDの基盤にUni-ID Libraを採用しましたが、OpenID Connectによって異なるシステム間でIDを統合でき、許諾管理が行えること、そして多要素認証によるセキュリティの強化はもちろん、パスワードレス認証やソーシャルログイン、シングルサインオンにも対応し、お客様の利便性に寄与することといった、Kintetsu-IDが求める機能要件を標準で満たしていたことが理由です。
また、共通IDは一度スタートしたら簡単にはやめることのできないサービスです。国内で高いシェアを持ち、継続的にソフトウェアが提供されるであろうことも重視しました。また、共通ID基盤構築後でも時々の状況に応じて柔軟にカスタマイズ可能であることも安心材料でした。
共通ID基盤を構築し、グループ各社にSaaSとしてサービス提供できる技術力を備えた近鉄情報システムの存在も大きな要因です。
お客様の個人情報をお預かりし、グループ内で展開していくことを考えると、しっかりセキュリティが確保された基盤で保持していく必要があります。セキュリティの専門家であるNRIセキュアが開発した製品であることも決め手となりました。

導入の効果
パッケージの標準仕様をベースに、専門家の助言を得ながら迅速に共通ID基盤を構築
 近鉄グループホールディングス株式会社 総合政策部デジタル推進室係長 吉山隼人氏
近鉄グループホールディングス株式会社 総合政策部デジタル推進室係長 吉山隼人氏
2022年春から構築を進めましたが、移行ではなく新規構築であることに加え、Uni-ID Libraは共通ID基盤に求める機能要件を満たしているパッケージソリューションであるため、カスタマイズは加えずに標準機能のみを利用する方針とし、結果としてスムーズにプロジェクトが進みました。
Uni-ID Libraはコンテナサービスとして構築可能なアーキテクチャであるためスモールスタートが可能で、構築後でも柔軟に拡張することができます。これから広がるサービスに非常にフィットした使い方ができます。
この基盤の上で、NRIセキュアのアドバイスを生かしながら連携予定の各社サービス担当と話し合いを重ね、IDの連携方式やユースケースを洗い出していきました。社内にID連携技術(Open ID Connect等)の専門家がおらず、アーキテクチャを知るところからのスタートでしたが、NRIセキュアから技術的な助言をいただきながら進めることができました。
やむを得ない事情で進捗が停滞する時期もありましたが、我々の都合に合わせた柔軟な支援体制を提供いただきました。問い合わせ窓口では技術に精通したエンジニアが対応をしてくれるため、質問にもその場で回答が得られ、迅速に進めることができました。
今後の展望
共通ID基盤を通じたデータ利活用で、顧客をより深く理解してグループの相乗効果に

Kintetsu-IDは、伊勢志摩エリアへのお出かけに使えるWebサービス「ぶらりすと」を皮切りに、KIPSアプリや都プラスアプリなど2025年3月時点で9サービスに導入されています。今後も各サービスとの連携を拡大していく予定です。
こうして各社のサービスをどんどん利用していただき、取得した属性情報をCDPに集約してどのような消費を行っているかを分析し、お客様をより深く理解していきたいと考えています。
当たり前かもしれませんが、ホールディングス本位ではなく、実際にサービスを運営するグループ各社にどんな利点があるかを考え、相手を主語にしてプロジェクトを進めていきました。この結果、多要素認証やパスワードレス認証によってセキュリティ強化と利便性の向上を同時に実現し、お客様がより便利に使える環境が実現できていると思います。
今後もKintetsu-IDを通してサービス連携を拡大し、「便利だな」と思えるサービスを増やすことで、Kintetsu-IDの会員数を増やし、お客様の一日に何回も近鉄グループのサービスが登場してグループ全体の相乗的な売り上げの拡大につなげていきたいと考えています。そのためにも、Uni-ID Libraが今後も高い品質で継続的に提供されていくことに期待しています。
※本文中の組織名、職名、概要図は2025年1月時点のものです。