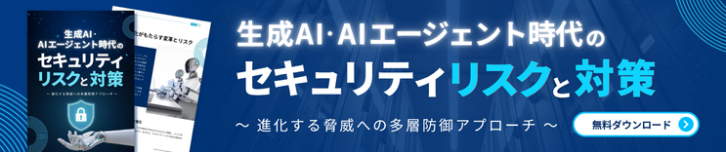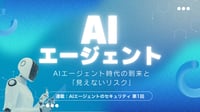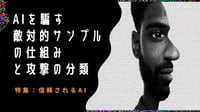専門誌だけでなく、テレビや新聞といった一般向けのメディアでさえ「生成AI」が話題となり、個人的にChatGPTなどを試す人も増えています。そんな中、どう生成AIに向き合い、どう活用するか模索を始めながら、漠然とした不安を抱いたり、活用法に悩んだりする企業は少なくないでしょう。
NRIセキュアも、まさに生成AI活用法を模索し続けている企業の1つです。主にマーケティング部門を率いる渡部 惣氏、全社横断の営業組織を率いる遠藤 良二氏らが中心となって、トライアンドエラーを重ねながら、セキュリティやガバナンスを確保した形でのAI活用に、本部内で取り組み始めています。
その際に力を借りたのが、生成AI活用法に関する研修やコンサル、コミュニティ活動「AI木曜会」を展開し、個人・法人のAI活用支援をしているMichikusa株式会社です。同社の代表取締役であり、AIを活用した業務効率化の指南役として知られているusutaku氏こと臼井拓水氏を招き、AI活用における課題や企業にもたらすインパクトについて語り合いました。
企業のAI導入を妨げる心理的・制度的な壁
 Michikusa株式会社 代表取締役 臼井 拓水氏
Michikusa株式会社 代表取締役 臼井 拓水氏
Q:今、日本企業における生成AI活用はどの程度進んでいるのでしょうか?
臼井:アメリカや中国、ドイツといった国々に比べると後れを取る面もありますが、グローバルで見ると平均以上で、確実に進んでいます。海外のAIスタートアップと話していても、日本はアメリカに次いで2番目に重要な市場と捉えられています。もはや、ある程度規模の大きな企業であれば、「AIを使っていかなければいけない」という認識は当たり前のように持たれているようです。特にこの2年で普及は進んでおり、PwCのデータによると、「AIを活用している」という企業は、2023年は0%、検討中の企業ですら8%でしたが、2025年は56%にまで増えています。
ただ、実際にどれだけ活用できているかとなると話は別です。「AIを導入しています」というポーズは見せているものの、社内でしっかり活用できている企業となるとまだ少ない印象です。
ただ、実際にどれだけ活用できているかとなると話は別です。「AIを導入しています」というポーズは見せているものの、社内でしっかり活用できている企業となるとまだ少ない印象です。
Q:活用が本格化しない理由は何だと思いますか?
臼井:ChatGPTが典型例ですが、AIは「この領域ならば絶対にこれ」というように特定の業務に特化しておらず、何でもできるが故に、どこで使えばいいのか分かりづらいのが理由の1つだと思います。
遠藤:とりあえず「AIを使おう」という手段と目的が逆転している状態から始まっているような状況があるのではないかと考えている。現状の業務をどう効率化し、改善していくか、それが会社にどんなインパクトを与えるか、というところから考える「効率化脳」の欠如もハードルの1つではないかと考えている。効率化脳というのはusutakuさんが主催している「AI木曜会」の中で出てきたキーワードですが、日本企業各社に効率化脳を持った人材がいれば、一気にAI活用が進むでしょう。業務効率を向上させ、もっと創造的な活動に自分の時間を振り向けたいのであれば、AIを活用しないわけにはいきません。もっと言ってしまうと、現状維持で十分だと考える、変革に慎重な姿勢が結果的にAI活用の妨げになってしまっていると思います。
臼井:AIを導入するメリットを最も感じているのは、多くの業務をこなしてスキルを身につけて成長したいと考える若者と、コストカットしたい経営陣です。それ以外の人たちにとってはAIを使うインセンティブは薄れがちです。これを乗り越えるには、AI推進と人事評価をリンクさせていく必要があると思います。これまで1時間かかっていた仕事を、AIを使って10分でできるようになれば、単純にアウトプットが6倍に増えます。にもかかわらず待遇が変わらないのでは、AIを使うメリットはあまり感じられません。
遠藤:人事評価制度や待遇まで考慮するとなると、CIOやCISOのように、役員レベルでAIの戦略的な活用を考えるポジションも必要になるでしょうか?
臼井:ええ、そうした企業さんは非常に増えています。業務の中でどうAIを活用するかを考える「AI推進担当」とは別に、社内のAI戦略を設計し、事業のAI化を推進する「CAIO」(Chief AI Officer)のようなポジションを置くケースも増えています。
セキュリティはもう一つの壁か、それとも促進を後押しする味方か
 NRIセキュアテクノロジーズ 事業戦略推進本部 マーケティング戦略部 部長 渡部 惣
NRIセキュアテクノロジーズ 事業戦略推進本部 マーケティング戦略部 部長 渡部 惣
渡部:「NRI Secure Insight 2024」によると、AI活用における課題の1位は「入力可能なデータの判断」で、2位が「ルールの不在、ルールを作る人材の不在」でした。3位には「出力されたアウトプットが不安定であること」が挙げられています。ルールや人材の不在に加え、漠然とした不安が重なって利活用が進まないのではと分析しています。少なくとも、AIに対しどんな用途でどんなデータを入力すべきか、すべきではないかというクライテリアをきっちり定めるべきでしょう。
臼井:私がお話しした中で、9割ほどは情報漏洩のリスク、セキュリティを気にしてAIを使わない印象がありました。ですが私は、セキュリティを理由にしてAIを使わないことこそ、いかに危険かを強調したいと思っています。
皆が川で洗濯をしていた時代に洗濯機の存在を知ったとすれば、いくら周りの人たちが「得体の知れない機械だ」と怖がったとしても、それを使うと思います。同じように、いくら会社側がAIを禁止しても、向上心を持ち、情報感度が高い優秀な人材であればあるほど使うでしょう。
このとき最も危険なのは、個人が会社に隠れ、エンタープライズ向けではないAIを無秩序に使うことで情報漏洩してしまうことです。事実、「会社ではAIを使えないので、私用の携帯でAIを使い、その結果を会社のパソコンに送ってしまう」といったケースを、裏側ではよく耳にします。
ですから、情報を漏洩させたくないのであれば、むしろ「使うなら、このように使いましょう」とルールを定め、セキュアなAIを導入することが、最も安全だと考えています。
皆が川で洗濯をしていた時代に洗濯機の存在を知ったとすれば、いくら周りの人たちが「得体の知れない機械だ」と怖がったとしても、それを使うと思います。同じように、いくら会社側がAIを禁止しても、向上心を持ち、情報感度が高い優秀な人材であればあるほど使うでしょう。
このとき最も危険なのは、個人が会社に隠れ、エンタープライズ向けではないAIを無秩序に使うことで情報漏洩してしまうことです。事実、「会社ではAIを使えないので、私用の携帯でAIを使い、その結果を会社のパソコンに送ってしまう」といったケースを、裏側ではよく耳にします。
ですから、情報を漏洩させたくないのであれば、むしろ「使うなら、このように使いましょう」とルールを定め、セキュアなAIを導入することが、最も安全だと考えています。
遠藤:かつてSaaSが普及し始めた当時にも、会社が認可していないSaaSを従業員が裏で使ってしまう「シャドーIT」が課題となりました。AIを巡っても同じような問題が起きていると捉えています。
まず社内においてAIのルールや規程類を整備し、会社として標準のAIサービスを定義して「使い倒してください」と解放し、もしAI戦略を推進する中でニーズを満たせないケースが出てくれば、申請と承認のワークフローに基づいてしっかりチェックした上で許可していくというプロセスを踏む。このやり方が、エンタープライズでは適していると思います。
まず社内においてAIのルールや規程類を整備し、会社として標準のAIサービスを定義して「使い倒してください」と解放し、もしAI戦略を推進する中でニーズを満たせないケースが出てくれば、申請と承認のワークフローに基づいてしっかりチェックした上で許可していくというプロセスを踏む。このやり方が、エンタープライズでは適していると思います。
渡部:車が性能を発揮し、スピードを出すためには強力なブレーキが必要なのと同じで、事業をドライブさせるためにセキュリティが必要です。生成AIに関しても同様に、どんどん利活用するためにルールを整備し、必要なセキュリティ対策を進めることが大事だと思います。
ただ、セキュリティを気にしすぎて何もしないのは、ガレージの中でブレーキを踏んでいるようなものであり、意味がありません。まずは一歩外に出て、ブレーキの効きを確かめながら少しずつスピードを出していくように、ちょっとずつ試す勇気が必要ではないかと思います。
usutakuさんがおっしゃったとおり、闇雲に恐れてAIを使わないことこそ一番のリスクであり、安全に使う仕掛けを作ってスモールスタートしていくことが重要だと思います。その意味でセキュリティは、AI活用を妨げる壁ではなく、利活用を促進するための仕組みだと言えるでしょう。
ただ、セキュリティを気にしすぎて何もしないのは、ガレージの中でブレーキを踏んでいるようなものであり、意味がありません。まずは一歩外に出て、ブレーキの効きを確かめながら少しずつスピードを出していくように、ちょっとずつ試す勇気が必要ではないかと思います。
usutakuさんがおっしゃったとおり、闇雲に恐れてAIを使わないことこそ一番のリスクであり、安全に使う仕掛けを作ってスモールスタートしていくことが重要だと思います。その意味でセキュリティは、AI活用を妨げる壁ではなく、利活用を促進するための仕組みだと言えるでしょう。
臼井:逆に言えば、セキュリティさえ担保できるのであれば企業側も安心して導入できるわけですから、AIビルダー側ももっとそこを押し出していくといいのかもしれませんね。
NRIセキュアの取り組みに見る、現場のリアルなAI活用

Q:NRIセキュアではどのようにAI活用を進めているのでしょうか?
渡部:NRIでは、まず2019年にグループ全体で「NRIグループAI倫理ガイドライン」を定め、2024年にはもう少し利活用の観点を加えた「NRIグループAI基本方針」を策定しました。同時に、2024年にはNRIグループの全社員が、AIにはどのようなリスクがあり、どのように利活用すべきかを学ぶ「AIリスク研修」を受講しました。
基本方針に紐づく「AI利用者向けリスク対応策」として利用上の重要なルールを定めており、「個人情報と機密情報は絶対に入力をしない」「AIから出てきたアウトプットはそのまま利用せず、必ず人が判断して編集・加工のうえ利用する」という二つを大原則として定めたほか、サービス・利用環境などで細かなルールも定めています。現場から新たに「こんなAIをこういう用途で使いたい」といった要望があれば、会社が用意したチェックリストで確認した上で申請し、審査を通すというプロセスを作っています。
さらに、グループ全体のルールを所管しているチームがAIの動向をウォッチし、AIに関するルールを細かくアップデートし、全社に通知しています。
基本方針に紐づく「AI利用者向けリスク対応策」として利用上の重要なルールを定めており、「個人情報と機密情報は絶対に入力をしない」「AIから出てきたアウトプットはそのまま利用せず、必ず人が判断して編集・加工のうえ利用する」という二つを大原則として定めたほか、サービス・利用環境などで細かなルールも定めています。現場から新たに「こんなAIをこういう用途で使いたい」といった要望があれば、会社が用意したチェックリストで確認した上で申請し、審査を通すというプロセスを作っています。
さらに、グループ全体のルールを所管しているチームがAIの動向をウォッチし、AIに関するルールを細かくアップデートし、全社に通知しています。
臼井:しっかりしたルールがなく曖昧なままにしてしまうと、どの情報は入力してもよく、どの情報はだめなのかといった事柄を個人に判断させることになってしまいますね。
Q:その中で、Michikusa社からどのような支援を受け、生かしているのでしょうか?
遠藤:NRIセキュアでは、CoEという正式な組織体ではありませんが、マーケティング戦略部と、ビジネス推進部とでCopilotやChatGPTなどを業務活用する取り組みを開始しました。その推進活動の中で、usutakuさんに教えを請おうと考え、Michikusaさんに相談させていただきました。
初学者向けの標準的な勉強会ではなく、どんな業務にどのくらい時間がかかっているかという「明細」と重点ポイントを洗い出した上で、我々の業務の特性に応じたMichikusaさんのベストプラクティスを教えていただくような勉強会にカスタマイズしていただきました。
YouTubeの動画などを見ると、GPTを使うにしても、高度なプロンプトを用意する必要があるのではないかとハードルを上げてしまいがちです。けれどusutakuさんに最初に「プロンプトはもちろん大事だけれども、それ以上に聞き方にコツがある」とおっしゃっていただき、我々の業務に置き換えた形で、AIへの聞き方のコツを教えていただきました。秘伝のタレを教えていただいたおかげで、業務の中でのAI活用がしやすくなり、活用の幅が広がっています。
また、本部内でもAIの利活用の事例をシェアする勉強会を実施しています。聞き専ではなく能動的に、「自分はどのように業務にAIを活用したか」を輪番でアウトプットしていく場で、統括本部長などマネージャー層も巻き込み、本部全体で進めてきました。会社の中での役職に関係なく、フラットにスタートして3ヶ月ほど続けてきた結果、AI活用に関しても筋肉質になり、洗練されてきたと思います。
初学者向けの標準的な勉強会ではなく、どんな業務にどのくらい時間がかかっているかという「明細」と重点ポイントを洗い出した上で、我々の業務の特性に応じたMichikusaさんのベストプラクティスを教えていただくような勉強会にカスタマイズしていただきました。
YouTubeの動画などを見ると、GPTを使うにしても、高度なプロンプトを用意する必要があるのではないかとハードルを上げてしまいがちです。けれどusutakuさんに最初に「プロンプトはもちろん大事だけれども、それ以上に聞き方にコツがある」とおっしゃっていただき、我々の業務に置き換えた形で、AIへの聞き方のコツを教えていただきました。秘伝のタレを教えていただいたおかげで、業務の中でのAI活用がしやすくなり、活用の幅が広がっています。
また、本部内でもAIの利活用の事例をシェアする勉強会を実施しています。聞き専ではなく能動的に、「自分はどのように業務にAIを活用したか」を輪番でアウトプットしていく場で、統括本部長などマネージャー層も巻き込み、本部全体で進めてきました。会社の中での役職に関係なく、フラットにスタートして3ヶ月ほど続けてきた結果、AI活用に関しても筋肉質になり、洗練されてきたと思います。
Q:実際の業務ではどのようにAIを活用していますか?
 NRIセキュアテクノロジーズ 事業戦略推進本部 ビジネス推進部 部長 遠藤 良二
NRIセキュアテクノロジーズ 事業戦略推進本部 ビジネス推進部 部長 遠藤 良二
遠藤:各メンバーの業務明細の洗い出しと、業務の重み付けを行ってみると、クリエイティブに資料を作る業務、と社内外の情報を検索する業務、例えばWeb上で営業先の情報を探したり、コンタクト履歴情報を検索・収集したりする業務、その二つに主に重点があることがわかりました。
後者に関しては、自分たちでRAGを開発し、社内ルールに準拠した社内リソースを検索できる環境を整え始めています。お客様との取引ログや提案内容、業績管理のドキュメントなど外部のAIには渡すことのできない内部情報の、検索性を高めています。
RAGの開発は、会社のルールの中で、AIによる業務活用に興味を持つメンバーで取り組みを開始し、それを部門内で使ってみるところから始めました。そして本部全体で使ってみるという形に発展させました。少しずつ範囲を広げながら、各現場のリクエストをRAGの中に組み込んでいます。もし社内にその情報がなければ、安全に隔離された環境に必要な情報を置いておき、RAGで検索できるよう設計しています。
後者に関しては、自分たちでRAGを開発し、社内ルールに準拠した社内リソースを検索できる環境を整え始めています。お客様との取引ログや提案内容、業績管理のドキュメントなど外部のAIには渡すことのできない内部情報の、検索性を高めています。
RAGの開発は、会社のルールの中で、AIによる業務活用に興味を持つメンバーで取り組みを開始し、それを部門内で使ってみるところから始めました。そして本部全体で使ってみるという形に発展させました。少しずつ範囲を広げながら、各現場のリクエストをRAGの中に組み込んでいます。もし社内にその情報がなければ、安全に隔離された環境に必要な情報を置いておき、RAGで検索できるよう設計しています。
渡部:マーケティング部門では主に、外部の情報収集や企業分析にChatGPT等を活用しています。ディープリサーチで広範かつ深い情報を収集し分析資料を作成しています。そしてその資料を社内の独自RAGの参照データとして利用し、社内と社外とで横断的に企業情報を検索できる環境を作っています。いわば、生成AIの二刀流です。
加えて、広告やサービス紹介ページなどのクリエイティブの作成でも活用しています。もっとも、出てきた答えをそのまま使うことはありません。まずたたき台を作ってもらい、問いを深めながら最終的なアウトプットを作成しています。おかげで、体感ですが、アウトプットを作るまでの時間が3〜4割は削減できているように思います。
加えて、広告やサービス紹介ページなどのクリエイティブの作成でも活用しています。もっとも、出てきた答えをそのまま使うことはありません。まずたたき台を作ってもらい、問いを深めながら最終的なアウトプットを作成しています。おかげで、体感ですが、アウトプットを作るまでの時間が3〜4割は削減できているように思います。
臼井:NRIセキュアさんのこうした取り組みはユニークなものだと思います。セキュリティを重視する会社はAIを使いたがらない一方、ガンガン活用している会社になると、いったんセキュリティは二の次となりがちです。
そんな中で、AIとセキュリティの両立に積極的に取り組んでいるケースはなかなかありません。NRIセキュアさんのように、セキュリティをしっかり固めた上で本気でAI利用を推進していく、つまり、どちらかを優先するのではなく両方に100%力を入れていく会社がどんどん出てきてほしいなと思います。
また、1年かけても変わらない企業もある中で、3ヶ月でこれだけ進展したのも、異例のスピードだと思います。チャレンジ精神のある企業風土でなければ、これだけ進むことはないでしょう。
そんな中で、AIとセキュリティの両立に積極的に取り組んでいるケースはなかなかありません。NRIセキュアさんのように、セキュリティをしっかり固めた上で本気でAI利用を推進していく、つまり、どちらかを優先するのではなく両方に100%力を入れていく会社がどんどん出てきてほしいなと思います。
また、1年かけても変わらない企業もある中で、3ヶ月でこれだけ進展したのも、異例のスピードだと思います。チャレンジ精神のある企業風土でなければ、これだけ進むことはないでしょう。
AI人材が活躍できる企業に求められる条件とは

遠藤:せっかくの機会ですからお伺いしたいのですが、NRIセキュアは、usutakuさんのようなAI活用人材を獲得していきたいと考えています。もし今usutakuさんが就職活動をするとしたら、どのような労働環境を求めますか?
臼井:まず確認したいのはPCのスペックですね。AIを扱う前提として、少なくとも現状では16GB程度は必要だと思っています。
メモリは、料理人にとってのキッチンや台所用具です。いくら腕利きのシェフを呼んでも、そこに投資せずに最高の料理を作ることなんて困難です。パソコンも同じで、優秀な人材にいいアウトプットをお客様に提供しようと考えるならPCには投資をした方がいいと思います。加えて、それによって社員のエンゲージメントが高まり、顧客からの受注が増えれば安いものです。
また、社内でAIを使えるかどうか、使えるとしたら何を使っているかも聞くでしょうね。エンタープライズ向けの有償プランを使えるのが絶対条件で、その上で、社内でAIトレーニングを実施しており、それに合格したら、毎月一定額まで好きなAIの費用に充てられる「AI補助金」のような制度があれば最高です。ただ、こうした例はまだほとんどないと思います。
もっと大事なことは、セキュリティのことを気にしなくてもAIを活用できる環境があること、そしてAIを活用してしっかりと成果を出した人が評価される環境が整っていることです。給与という形もいいですが、社内における名誉や、次の成長につながるより難しい業務にチャレンジできる文化などがあれば、いい会社だなと感じると思います。
メモリは、料理人にとってのキッチンや台所用具です。いくら腕利きのシェフを呼んでも、そこに投資せずに最高の料理を作ることなんて困難です。パソコンも同じで、優秀な人材にいいアウトプットをお客様に提供しようと考えるならPCには投資をした方がいいと思います。加えて、それによって社員のエンゲージメントが高まり、顧客からの受注が増えれば安いものです。
また、社内でAIを使えるかどうか、使えるとしたら何を使っているかも聞くでしょうね。エンタープライズ向けの有償プランを使えるのが絶対条件で、その上で、社内でAIトレーニングを実施しており、それに合格したら、毎月一定額まで好きなAIの費用に充てられる「AI補助金」のような制度があれば最高です。ただ、こうした例はまだほとんどないと思います。
もっと大事なことは、セキュリティのことを気にしなくてもAIを活用できる環境があること、そしてAIを活用してしっかりと成果を出した人が評価される環境が整っていることです。給与という形もいいですが、社内における名誉や、次の成長につながるより難しい業務にチャレンジできる文化などがあれば、いい会社だなと感じると思います。
遠藤:CoEやCAIOのような制度の整備に加え、そんな企業文化を醸成するポイントは何だと思いますか?
臼井:やはり、代表が「AIを使おう。」と言っているかどうかは大きいと思います。一部の人たちだけでなく、会社の代表が言うことで、文化が広がり、人事評価の改革にもつながっていくと思います。基本的にAI活用は、経営層を巻き込み、トップダウンで進めなければなかなか推進できません。そんな中で、NRIセキュアさんのような現場が積極的に推進するやり方は非常にいい事例になると思います。
Q:この先、人材を確保する上でもAIが使える環境は不可欠となりますね。
臼井:しっかりと働き、成長したいと考える人でAIを使わない人はいないと考えています。あるいは、絶対AIに代替されない人材、たとえば体力やコミュニケーション能力を備えたスーパー営業職を目指すか、ですね。それ以外の人材はAIで代替できてしまう可能性が高いです。
渡部:AI自体が日進月歩で進化しており、使っている会社と使っていない会社の格差もとんでもなく拡大していくと思います。もはやAIを使わないこと自体がリスクであり、使わないという選択肢はありません。まずは小さくてもいいから一歩、AI活用を進めてみるのがいいと思います。少しでも試す勇気とセキュリティ環境を整えて、スモールステップで進めることが企業に求められていると思います。
遠藤:営業側の観点では、誰でもできる作用はAIを活用し、我々営業は営業ならではの価値を提供できる活動にいっそう従事できる環境整備を目指します。例えば、過去の社内リソースの検索業務。ファイルサーバー内を探すのに要する時間は、1日あたり5分程度かもしれませんが、“ちりも積もれば山となる”で、1年で考えると大きなロスになると考えています。これらの無駄をAI活用によりなくしお客様とのコミュニケーションなど、人間にしかできない高付加価値な業務に全力で取り組める。そのための環境を、これから半年以内には完成させたいと思っています。
渡部:当社では、AIエージェントを用いた開発をセキュアに進めていくための支援を行う「AI Yellow Team」、社外向けのAIサービスに対するセキュリティ診断を行う「AI Red Team」、AIを監視して攻撃を受けたら検知する「AI Blue Team」といったサービスを提供しています。セキュリティに不安を覚える方がいれば、こうしたサービスをご活用いただくのもいいかと思います。
Q:最後に、それでもAI活用に不安を抱く企業へのアドバイスがあればお願いします。

臼井:そもそも、AIを導入するかしないかを検討するのではなく、導入する前提で考えなければいけない時代です。AIに代替されない業務で生きていく会社を目指すとしても、AIを導入していなければ、何がAIにはできないのかが理解できません。ですからやはり実際に触れ、理解していく必要があると思います。
渡部:AIは、どんどん進化を続ける新しい技術であり、自分の能力を拡張してくれる前向きな、楽しい存在だと思います。それを、セキュリティを理由に活用しないのはもったいない話です。ぜひ「何ができるんだろう」と興味を持ち、usutakuさんのXのアカウントやYouTubeチャンネル、Michikusa株式会社のコンテンツを見たりして一歩進めてみることが大事かなと思います。セキュリティ面での不安についてはNRIセキュアのブログがありますから、それらも参考に、前向きな情報収集を進めていただければと思います。
遠藤:usutakuさんも繰り返しおっしゃっていますが、AIを活用するのはもう当たり前。AIに代替されていく業務は増えていくでしょう。今までやってきた仕事がAIに代替されていく中で、自分は何をもって価値を出していくのか、今後はアイデアや実行力が試されてくる時代になっていくと思います。危機感を持ちながらもAIの活用法を学び推進していければと考えています。