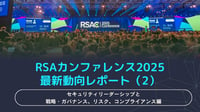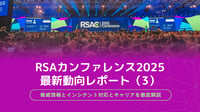Google Cloud Next Tokyo '25が8月5日、6日の2日間にわたって、東京ビッグサイトで開催されました。生成AIとAIエージェントがビジネスをどう変革するのか。Googleの新たなAI戦略、そして未来への展望を、現地参加の視点からレポートさせていただきます。
Google Cloud Next Tokyoとは
「Google Cloud Next」は、Googleがラスベガスで開催する年次カンファレンスで、クラウド技術、AI、データ分析、セキュリティなどに関する最新情報を発表する場です。Googleのエンジニアやプロダクトリーダーが登壇し、世界中の企業や開発者に向けて、新技術や戦略が紹介されています。
「Google Cloud Next Tokyo」はその日本版であり、日本市場向けにローカライズされた内容が特徴です。「Google Cloud Next」で発表された内容の振り返りはもちろんのこと、日本企業の導入事例や、国内の課題に即したソリューションが紹介され、実践的な学びが得られる場となっています。
2025年のテーマは「生成AIとAIエージェントによるビジネス変革」で、グローバルの発表内容をベースにしつつ、日本企業の取り組みや課題に焦点を当てた構成となっていました。

基調講演
1日目の基調講演では、Google Cloudを活用してどのように革新的なAIエージェントを構築できるのか、その具体的なヒントを事例やデモを交えて紹介する内容でした。
AIエージェント元年
2025年は「AIエージェント元年」と位置づけられ、Googleは業務に深く組み込めるAIエージェントの可能性を提示しました。AIエージェントは、情報収集から意思決定、実行までを一貫して担い、業務の効率化だけでなくスキルの補完にも貢献します。複数のツールを横断して情報を集めて業務を代行することで、企業の競争力を高める新たな働き方が実現されつつあります。

Geminiの進化と国内展開
Googleの最新AIモデル「Gemini 2.5」シリーズは、推論精度と処理速度が大幅に向上し、マルチモーダル対応で画像・音声・動画も扱えるようになりました。
講演の中では「Gemini 2.5 Flashの東京リージョンが展開」されたことが発表され、日本国内でのデータ処理が可能となり、コンプライアンス面でも安心して導入できる環境が整ったことが強調されました。このように、企業のAI活用がより現実的かつ迅速に進む土台が築かれています。他にも、Imagen、Veo3、Chirp3、Lyria2などのモデルについても紹介されました。
- 実は、筆者は2週間ほど前に「Generative AI Leader」の試験に合格したばかりなので、講演中に出てくるモデルや生成AIサービスについては全て理解できました。もし、受けていなければ講演の内容についていけなかったと思います。聴講の解像度を上げるためにも、「Generative AI Leader」を受験しておいてよかったと思いました。

Agent Development Kit(ADK)による独自のAIエージェント開発
GoogleはAIエージェントの開発・運用を支援する「Agent Development Kit(ADK)」を提供しています。ADKにより、開発者は煩雑なコーディングをせずに、高性能なAIエージェントを短期間で開発することが可能になります。講演ではADKの事例がいくつか紹介されました。デジタル庁は、AIエージェントにより半自動化されたガバメントクラウドの移行レビューを実施。日本テレビでは、番組企画をサポートするAIエージェントを開発。メルカリでは、全従業員向けのデータ分析用AIエージェントを開発。各社とも自社の業務に合った独自のAIエージェントの開発に注力しています。
Google Agent Spaceによる業務革新
Google Agent Spaceにより、複数のエージェントが連携しながら複雑な業務を自律的に遂行することが可能になります。実施されたデモでは、エレベーターの保守業務を例に、問い合わせ対応から故障予測、担当者のアサインまでをAIにより自動化しており、人とAIが協業する未来の働き方が鮮明に描かれました。
講演の中では「Google Agent Spaceの日本リージョンへの対応」が予定されていることが発表され、データインデックス作成から検索、アクションまでのすべての操作が国内で完結するようになります。
Agent Spaceの活用事例としては、MIXIはGoogle Agent Spaceを活用し、社内情報の横断検索やAIエージェントの集約運用を進め、業務効率と創造性の向上を実現。メルカリはカスタマーサポートにAIを導入し、24時間対応や感情分析による応答品質の向上を図っています。博報堂は全社的にGeminiを導入し、若手社員による逆メンター制度でAI活用を促進。各社がAIを共働者として位置づけ、業務改革を加速させています。
Google WorkspaceとGeminiによる創造
Google Workspaceは、生成AI「Gemini」との統合により、日常業務の在り方を大きく変えつつあります。メールやドキュメント、スプレッドシート、会議など、あらゆる業務ツールにAIが組み込まれ、情報収集、要約、翻訳、分析、提案といった作業が数分で完了します。講演中のデモでは、GeminiのDeep Research機能を使って、健康志向とサステナビリティをテーマにした新商品企画を遂行する様子が紹介されました。
導入事例としては、博報堂では社内のナレッジ活用や意思決定の迅速化にGeminiを活用し、業務の質とスピードを飛躍的に向上させています。札幌市では全庁へのGoogle Workspace導入により、部門間のコラボレーションが促進された様子が紹介されました。
講演の最後には「Generative AI Leader試験が日本語対応」、さらに全認定試験の受験料が期間限定で50%オフと発表されました。
所感
AIがもはや未来の話ではなく、今現在の私たちの働き方を変え始めていることを実感させてくれる内容でした。特にGeminiの進化とGoogle Workspaceとの統合によって、日常業務が驚くほど効率化され、創造性を引き出すツールへと変貌している点が印象的でした。
AIエージェントが複雑な業務を自律的に遂行するデモは、「人とAIの協業」の可能性を示しており、企業だけでなく自治体や教育現場にも普及する様子をイメージできました。
エンジニアとしては、AIエージェントをどう活かし、なければ自分たちで作るという発想と技術力を持っておく必要があることを強く感じました。
会場の様子
会場の様子をたっぷり紹介していきたいと思います。
こちらは認定資格者ラウンジで、Google Cloud認定資格の取得者が入ることができます。
全冠取得者は、Google Pixel9が当たるガラガラの抽選に挑戦できます。
筆者は惜しくもPixel9は当たりませんでしたが、Tシャツとタオルが当たりました。

会場は全体的に緑が多い気がしました。自然が溢れていてよいですね。
こちらはAIバスケットボールコーチで、シュートフォームを分析してアドバイスしてくれます。
 NRIのブースも発見しました。とても活気にあふれていました。
NRIのブースも発見しました。とても活気にあふれていました。
またガラガラの抽選がありました。ここでは、招待コードを持っていると挑戦できるようです。筆者は持っていたので挑戦し、見事スケッチブックを手に入れました。
こちらはクイズチャレンジです。回答用のパソコンが並べられており、アプリやセキュリティなど自分の得意な分野を選び、分野にちなんだ10問のクイズに挑戦します。Google資格全冠の筆者が挑戦しないわけにはいかないので、セキュリティ分野で挑戦しました。
もちろん合格することができ、景品として布製のステッカーを頂きました。

会場から少し離れたところには、パートナーラウンジがありました。Google Cloudのパートナー企業に勤めていれば、事前に申し込みすることで入ることができます。
お菓子や飲み物、さらにはミーティングスペースまで完備されていました。こういう場所があると、急なミーティングの時嬉しいですね。
 会場にはワゴンカーも設置されており、ここで食事の調達もできました。
会場にはワゴンカーも設置されており、ここで食事の調達もできました。
おわりに
Google Cloud Next Tokyo '25は、AIが業務効率化の枠を超え、人と協働する「共働者」として社会に浸透し始めていることを実感させるイベントでした。Geminiの進化とGoogle Workspaceとの統合、Agent Spaceによる業務自動化など、技術の進歩だけでなく、それをどう活かすかという思想が随所に込められていました。企業だけでなく自治体や教育現場にも広がる導入事例は、AIが日本社会全体の生産性と創造性を高める可能性を示しています。
2026年も同会場で開催されることが確定しています。目覚ましい進化をしている生成AIの可能性を模索するために、ぜひ来年足を運んでいただければと思います。